
ストリーミングゲームサービス「Google Stadia」の料金体系 [クラウドサービス]
スポンサードリンク
速報:Google Stadiaは月9.99ドル、日本含まぬ14か国で11月開始。初期タイトル発表 - Engadget 日本版
Googleがストリーミングゲームサービス「Stadia」の詳細を発表し、料金体系についても明らかになった。
まず、サービスの開始だが、今年2019年11月からで、日本を含まない世界14か国でスタートする。
以前、「Google Stadia」に関して取り上げた時に、料金体系は従量制にせざるを得ないのではないかと書いたが、発表内容を見ると、一応定額料金プランは存在するようだ。
ただし、定額料金で遊べる内容には制限があり、ハイエンドのゲームについては、やはり事実上従量制にせざるを得ない苦悩がうかがえる。
詳しく見てゆこう。
定額制のサブスクリプションプラン「Stadia Pro」は月9.99ドルとなっているが、これで一部のタイトルが遊び放題(具体的なタイトルは未発表)となるが、それ以外の大半のタイトルは買い切り制で、ただし一部は割引料金が適用されるとのこと。
2020年以降には、月課金がないかわりに遊び放題タイトルなし、割引なし、購入したゲームのみ遊べるベースプランも提供されるそうだが、こちらは、画質音質も1080p 60fps映像・2ch音声に制限される。
サブスクリプションプラン「Stadia Pro」では、画質音質は、4K HDR 60fps映像・5.1ch音声対応となっていることを考えると、「Stadia Pro」の月9.99ドルという料金は、ゲームプロバイダへの支払いよりは、ほぼ4K HDRのゲームプラットフォームの維持費ととらえる方が正しいようだ。
ゲームを始めるには、低遅延で遊べるWi-Fi接続のStadiaコントローラが必要だが、これが一つ69ドル。
さらに、「Google Stadia」のスターターキットとも言える「Stadia Founder's Edition」が、129ドルで発売される。
これは、テレビで遊ぶためのChromecast Ultra (4K HDR対応, 59ドル)、3か月分のStadia Proサブスクリプション x2(片方は他ユーザーへのプレゼント専用)、独占でStadia Name (ユーザー名)を確保できる権利が含まれ、「総額300ドル分の価値」があるという。
当然だが、すでに「Chromecast Ultra」を持っている人間は、それを利用でき、わざわざ「Stadia Founder's Edition」を買う必要まではない。
現時点で、公開されているタイトルは次の通りだが、今後続々追加発表される予定。
・Dragon Ball Xenoverse 2
・Doom Eternal
・Doom (2016)
・Rage 2
・The Elder Scrolls Online
・Wolfenstein: Youngblood
・Destiny 2 (ファウンダーズエディション購入者は過去DLC含み無料、他プラットフォームからクロスセーブあり)
・Get Packed (Stadia独占)
・Grid
・Metro Exodus
・Thumper
・Farming Simulator 19
・Baldur's Gate 3
・Power Rangers: Battle for the Grid
・Football Manager
・Samurai Shodown
・Final Fantasy XV
・Tomb Raider Definitive Edition
・Rise of the Tomb Raider
・Shadow of the Tomb Raider
・NBA 2K, Borderlands 3
・Gylt (Stadia独占)
・Mortal Kombat 11
・Darksiders Genesis
・Assassin's Creed Odyssey
・Just Dance
・Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
・Tom Clancy's The Division 2
・Trials Rising
・The Crew 2
このうち、「Stadia Pro」で遊び放題になるタイトルは明らかになっていないが、Doomシリーズとか、Final Fantasy XVとか、Tomb Raiderシリーズなどの古い作品も多いので、そうした3Dエンジンの負荷が軽いゲームが、遊び放題になるのかもしれない。
ただし、Founder's Edition購入者には、新しいゲームである「Destiny 2」が遊び放題になることは確定しているという。
「Destiny 2」は、最近の3Dゲームなので、サーバのグラフィックスエンジンの負荷はかなり重いはずで、このゲームがどの程度、安定して運用できるかが、「Google Stadia」成功の試金石となりそうだ。
とはいえ、全体的に見て、提示された料金プランは、予想した範囲を逸脱しない、穏当な設定となった。
PS4のようなゲーム機は買わなくてもいい、というのが売りだったが、実際には、全く何も買わなくても始められるわけではなく、Chromecast Ultraやコントローラの購入に約200ドルが必要で、「初期費用は、ソニーPS5の半額ぐらいで済みます」という程度の意味しかないだろう。
あとは、個別のゲームの買い切り料金が、PS5などのゲームタイトルの料金に比べて、どの程度安く設定されるか次第だろう。
最新の本格的な4K HDR/3Dゲームを楽しみたければ、毎月約1,100円を支払い、その上で、各ゲームを個別に購入する必要があるのだから、毎月新作ゲームを1本は買うコアユーザーを仮定しても、PS5のゲームタイトルより1,000円ぐらいは安くないと、「Stadia Pro」にメリットを感じにくい気がするな。
あと、気になるのは、4K HDRでゲームを楽しむためには、35Mbpsの速度が安定して出る必要があるそうだが、となると、基本は光回線が必要。
日本や韓国ならともかく、欧米で、そんな高速で安定した光回線サービスを提供できる国が、どれだけあるのだろうか?
まずは、Googleのお手並み拝見、というところか。
関連記事:
Googleの「Stadia」はビジネスとして成立するのか?(2):トドのつまりは・・・ V2:So-netブログ
スポンサードリンク
速報:Google Stadiaは月9.99ドル、日本含まぬ14か国で11月開始。初期タイトル発表 - Engadget 日本版
Googleがストリーミングゲームサービス「Stadia」の詳細を発表し、料金体系についても明らかになった。
まず、サービスの開始だが、今年2019年11月からで、日本を含まない世界14か国でスタートする。
以前、「Google Stadia」に関して取り上げた時に、料金体系は従量制にせざるを得ないのではないかと書いたが、発表内容を見ると、一応定額料金プランは存在するようだ。
ただし、定額料金で遊べる内容には制限があり、ハイエンドのゲームについては、やはり事実上従量制にせざるを得ない苦悩がうかがえる。
詳しく見てゆこう。
定額制のサブスクリプションプラン「Stadia Pro」は月9.99ドルとなっているが、これで一部のタイトルが遊び放題(具体的なタイトルは未発表)となるが、それ以外の大半のタイトルは買い切り制で、ただし一部は割引料金が適用されるとのこと。
2020年以降には、月課金がないかわりに遊び放題タイトルなし、割引なし、購入したゲームのみ遊べるベースプランも提供されるそうだが、こちらは、画質音質も1080p 60fps映像・2ch音声に制限される。
サブスクリプションプラン「Stadia Pro」では、画質音質は、4K HDR 60fps映像・5.1ch音声対応となっていることを考えると、「Stadia Pro」の月9.99ドルという料金は、ゲームプロバイダへの支払いよりは、ほぼ4K HDRのゲームプラットフォームの維持費ととらえる方が正しいようだ。
ゲームを始めるには、低遅延で遊べるWi-Fi接続のStadiaコントローラが必要だが、これが一つ69ドル。
さらに、「Google Stadia」のスターターキットとも言える「Stadia Founder's Edition」が、129ドルで発売される。
これは、テレビで遊ぶためのChromecast Ultra (4K HDR対応, 59ドル)、3か月分のStadia Proサブスクリプション x2(片方は他ユーザーへのプレゼント専用)、独占でStadia Name (ユーザー名)を確保できる権利が含まれ、「総額300ドル分の価値」があるという。
当然だが、すでに「Chromecast Ultra」を持っている人間は、それを利用でき、わざわざ「Stadia Founder's Edition」を買う必要まではない。
現時点で、公開されているタイトルは次の通りだが、今後続々追加発表される予定。
・Dragon Ball Xenoverse 2
・Doom Eternal
・Doom (2016)
・Rage 2
・The Elder Scrolls Online
・Wolfenstein: Youngblood
・Destiny 2 (ファウンダーズエディション購入者は過去DLC含み無料、他プラットフォームからクロスセーブあり)
・Get Packed (Stadia独占)
・Grid
・Metro Exodus
・Thumper
・Farming Simulator 19
・Baldur's Gate 3
・Power Rangers: Battle for the Grid
・Football Manager
・Samurai Shodown
・Final Fantasy XV
・Tomb Raider Definitive Edition
・Rise of the Tomb Raider
・Shadow of the Tomb Raider
・NBA 2K, Borderlands 3
・Gylt (Stadia独占)
・Mortal Kombat 11
・Darksiders Genesis
・Assassin's Creed Odyssey
・Just Dance
・Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
・Tom Clancy's The Division 2
・Trials Rising
・The Crew 2
このうち、「Stadia Pro」で遊び放題になるタイトルは明らかになっていないが、Doomシリーズとか、Final Fantasy XVとか、Tomb Raiderシリーズなどの古い作品も多いので、そうした3Dエンジンの負荷が軽いゲームが、遊び放題になるのかもしれない。
ただし、Founder's Edition購入者には、新しいゲームである「Destiny 2」が遊び放題になることは確定しているという。
「Destiny 2」は、最近の3Dゲームなので、サーバのグラフィックスエンジンの負荷はかなり重いはずで、このゲームがどの程度、安定して運用できるかが、「Google Stadia」成功の試金石となりそうだ。
とはいえ、全体的に見て、提示された料金プランは、予想した範囲を逸脱しない、穏当な設定となった。
PS4のようなゲーム機は買わなくてもいい、というのが売りだったが、実際には、全く何も買わなくても始められるわけではなく、Chromecast Ultraやコントローラの購入に約200ドルが必要で、「初期費用は、ソニーPS5の半額ぐらいで済みます」という程度の意味しかないだろう。
あとは、個別のゲームの買い切り料金が、PS5などのゲームタイトルの料金に比べて、どの程度安く設定されるか次第だろう。
最新の本格的な4K HDR/3Dゲームを楽しみたければ、毎月約1,100円を支払い、その上で、各ゲームを個別に購入する必要があるのだから、毎月新作ゲームを1本は買うコアユーザーを仮定しても、PS5のゲームタイトルより1,000円ぐらいは安くないと、「Stadia Pro」にメリットを感じにくい気がするな。
あと、気になるのは、4K HDRでゲームを楽しむためには、35Mbpsの速度が安定して出る必要があるそうだが、となると、基本は光回線が必要。
日本や韓国ならともかく、欧米で、そんな高速で安定した光回線サービスを提供できる国が、どれだけあるのだろうか?
まずは、Googleのお手並み拝見、というところか。
関連記事:
Googleの「Stadia」はビジネスとして成立するのか?(2):トドのつまりは・・・ V2:So-netブログ
人気ブログランキングへ |
スポンサードリンク

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16eebc43.964832a0.16eebc44.d654ad9a/?me_id=1349740&item_id=10000719&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsokutei%2Fcabinet%2F05716971%2F4948872414739.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsokutei%2Fcabinet%2F05716971%2F4948872414739.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f8337e.cb31a7f0.08f4f1bd.c6df19a2/?me_id=1213310&item_id=18350576&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5716%2F4902370535716.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5716%2F4902370535716.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)



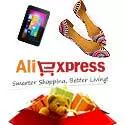

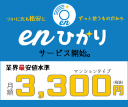

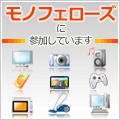



コメント 0