
ニコンのコンデジ「COOLPIX S9500」の使用レポート [デジタルカメラ]
スポンサードリンク
「COOLPIX S9500」に関しては、ダイソーで買ったこちらのちょうどいいサイズのフック付きクッションケース(たばこケースとして売られているもの)に入れ、ズボンのベルトにフックでぶら下げることにした。
ストラップホールには、ダイソーのスプリングストラップを取り付けて、反対側のクリップはクッションケースを挟みこんで、カメラを落としても地面まで落ちないようにしたのは、私がスマホでいつもやっていることだ。
COOLPIX S9500 | ニコンイメージング
一応使う準備は出来たので、ニコンのコンデジ「COOLPIX S9500」を、実際に使ってみよう。
まず、HDR撮影については、ダイヤルで逆光モードにし、メニューでHDRを有効にすると使えるが、カシオ「EX-ZR300」、ソニー「DSC-WX350」に比べても、暗部の潰れが小さく、日が暮れてからの街中の撮影には、威力を発揮しそうだ。
最大3枚の露出を変えた写真の合成ということで、効果も高いようだ。
ただ、暗所でのシャッター速度も遅めだし、シャッターのリリースタイムラグも大きめなので、撮影時にはカメラをしっかり固定して、シャッターを押す時に本体がぶれないように注意が必要だ。
また、撮影後、保存が完了するまでの時間が非常に長いのも玉に傷。「EX-ZR300」の倍近くかかっている印象だから、次々撮影したいときには困るだろう。
街歩きでも使ってみた。
最初にうろたえたのが、駅構内でオート撮影したら、いきなりポップアップ式のフラッシュが起き上がり、フラッシュを炊いてしまったこと。
よく考えれば分かるのだが、フラッシュがポップアップ式で隠されているとは思いもしなかったな。
普段は、フラッシュは一切使わないので、フラッシュは無効化し、その後は撮影を続けた。
バッテリーの撮影枚数は、約230コマ(EN-EL12使用時)となっていたが、中古でバッテリーもヘタっているようで、バッテリーの持ちは悪い。
結局、3時間ぐらいで、100枚ほど撮影したところでシャットダウンしてしまい、あとは、別のデジカメで撮影することになった。
USB端子が特殊なので、これ専用のケーブルを持ち歩かないと、モバイルバッテリーからの充電もできないし、うーん、これでは街歩き用には実用にならないな。
ただ、HDR撮影の画質は、これまで触った製品では良さそうなので、ビジネスバッグに入れておいて、出張などの後に、夜に街歩きする際に使ってみようと思う。
それなら、バッテリーがあまり持たないのもそれほど弱点にならないし、HDR撮影に強いメリットも生きるからだ。
バッテリーの持ちの悪さも分かりながら、最大の魅力を感じたのは、パソコン経由でGoogleフォトに写真を取り込んだ時だ。
取り込んだ途端、Googleフォト上では、GPSの位置情報をもとに、地名どころか、撮影した施設名で自動的にタグ付けされるらしく、
何のアルバム整理も不要となる。
ソニーのDSC-WX350も、スマホの位置情報を、転送した画像のタグ情報に自動書き込みしてくれるから、Googleマップにアップロードすると同じことはできるように見えるのだが、実際のところ、カメラをスマホとを一緒に持ち歩かないと、誤った位置情報がタグ付けされたり、スマホの電源が切れたり、GPSがオフになったりして、位置情報が付与されないことも多々あり、自分でGPS情報を取る「COOLPIX S9500」と同等の安心感とはいかない。
ただ「COOLPIX S9500」のバッテリーも持ちが悪いのは、ひょっとしたら、このGPSや電子コンパスを内蔵していて、電源OFF状態でも常に動いているせいかもしれないと思うと、痛しかゆしだ。
関連記事:
ニコンのコンデジ「COOLPIX S9500」のセットアップ:トドのつまりは・・・ V2:So-netブログ
スポンサードリンク
「COOLPIX S9500」に関しては、ダイソーで買ったこちらのちょうどいいサイズのフック付きクッションケース(たばこケースとして売られているもの)に入れ、ズボンのベルトにフックでぶら下げることにした。
ストラップホールには、ダイソーのスプリングストラップを取り付けて、反対側のクリップはクッションケースを挟みこんで、カメラを落としても地面まで落ちないようにしたのは、私がスマホでいつもやっていることだ。
COOLPIX S9500 | ニコンイメージング
一応使う準備は出来たので、ニコンのコンデジ「COOLPIX S9500」を、実際に使ってみよう。
まず、HDR撮影については、ダイヤルで逆光モードにし、メニューでHDRを有効にすると使えるが、カシオ「EX-ZR300」、ソニー「DSC-WX350」に比べても、暗部の潰れが小さく、日が暮れてからの街中の撮影には、威力を発揮しそうだ。
最大3枚の露出を変えた写真の合成ということで、効果も高いようだ。
ただ、暗所でのシャッター速度も遅めだし、シャッターのリリースタイムラグも大きめなので、撮影時にはカメラをしっかり固定して、シャッターを押す時に本体がぶれないように注意が必要だ。
また、撮影後、保存が完了するまでの時間が非常に長いのも玉に傷。「EX-ZR300」の倍近くかかっている印象だから、次々撮影したいときには困るだろう。
街歩きでも使ってみた。
最初にうろたえたのが、駅構内でオート撮影したら、いきなりポップアップ式のフラッシュが起き上がり、フラッシュを炊いてしまったこと。
よく考えれば分かるのだが、フラッシュがポップアップ式で隠されているとは思いもしなかったな。
普段は、フラッシュは一切使わないので、フラッシュは無効化し、その後は撮影を続けた。
バッテリーの撮影枚数は、約230コマ(EN-EL12使用時)となっていたが、中古でバッテリーもヘタっているようで、バッテリーの持ちは悪い。
結局、3時間ぐらいで、100枚ほど撮影したところでシャットダウンしてしまい、あとは、別のデジカメで撮影することになった。
USB端子が特殊なので、これ専用のケーブルを持ち歩かないと、モバイルバッテリーからの充電もできないし、うーん、これでは街歩き用には実用にならないな。
ただ、HDR撮影の画質は、これまで触った製品では良さそうなので、ビジネスバッグに入れておいて、出張などの後に、夜に街歩きする際に使ってみようと思う。
それなら、バッテリーがあまり持たないのもそれほど弱点にならないし、HDR撮影に強いメリットも生きるからだ。
バッテリーの持ちの悪さも分かりながら、最大の魅力を感じたのは、パソコン経由でGoogleフォトに写真を取り込んだ時だ。
取り込んだ途端、Googleフォト上では、GPSの位置情報をもとに、地名どころか、撮影した施設名で自動的にタグ付けされるらしく、
何のアルバム整理も不要となる。
ソニーのDSC-WX350も、スマホの位置情報を、転送した画像のタグ情報に自動書き込みしてくれるから、Googleマップにアップロードすると同じことはできるように見えるのだが、実際のところ、カメラをスマホとを一緒に持ち歩かないと、誤った位置情報がタグ付けされたり、スマホの電源が切れたり、GPSがオフになったりして、位置情報が付与されないことも多々あり、自分でGPS情報を取る「COOLPIX S9500」と同等の安心感とはいかない。
ただ「COOLPIX S9500」のバッテリーも持ちが悪いのは、ひょっとしたら、このGPSや電子コンパスを内蔵していて、電源OFF状態でも常に動いているせいかもしれないと思うと、痛しかゆしだ。
関連記事:
ニコンのコンデジ「COOLPIX S9500」のセットアップ:トドのつまりは・・・ V2:So-netブログ
人気ブログランキングへ |
スポンサードリンク


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1418718f.5d283ddf.14187190.48091dbd/?me_id=1295474&item_id=10203386&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwonderrex%2Fcabinet%2F6457%2Fav%2F66-25%2F569-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwonderrex%2Fcabinet%2F6457%2Fav%2F66-25%2F569-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)



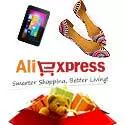

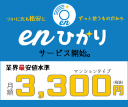

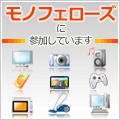



コメント 0